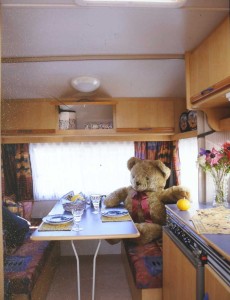日高と富良野を結ぶ国道237号線沿いにある「日高沙流川オートキャンプ場」は、日高山脈の麓を流れる沙流川(さるがわ)のほとりに開かれた町営キャンプ場。自然豊かなロケーションと施設利用費1人100円+オートサイト1300円~という低料金が、このキャンプ場の大きな魅力です。
広大な敷地内には、クルマの乗り入れが可能な4タイプのオートキャンプサイトが合計100区画用意されています。広さ110㎡のAサイト(10区画/1泊2500円)は、普通車2台分の駐車スペースがあり、大型キャンピングカーやキャンピングトレーラーでの利用も可能です。広さ100㎡のBサイト(49区画/1泊1900円)は、クルマ1台+テント・タープ各1張りが目安の一般的なオートサイト。Cサイト(20区画/1泊1300円)は、好きな場所にクルマを止めて設営できるオートフリータイプで、こちらのサイトのみペット同伴可能となっています。そのほかに、広さ100㎡の電源サイト(21区画/1泊3000円)もあり、キャンプスタイルに合わせて好みのサイトを選ぶことができます。
キャンプサイトは、豊かな緑と背の高い木々に囲まれた林間に開かれていて、どこに設営しても落ち着いた雰囲気の中でキャンプを楽しめます。場内には、キャンプ場利用者が無料で使用できるドッグランも完備。ターザンロープなどを設置したアスレチックコーナーで子供を遊ばせられるほか、場内を流れる水路や隣接する沙流川で水遊びも楽しめます。日帰り温泉施設も徒歩圏内で、スーパーやガソリンスタンドのある日高市街までも約1km。ワンコ連れ、ファミリー、夫婦、ソロまで、どんなキャンパーにもマッチする、自然と快適性のバランスが取れたキャンプ場です。
お盆と連休を除く日曜日から金曜日は、駐車場での車中泊(施設維持費1人100円、普通車700円、軽自動車400円)も可能。タープやイス・テーブルの使用、BBQ、焚き火などは禁止ですが、炊事場やトイレの利用、ゴミ処理はできますので、クルマ旅の手軽な宿泊地としても便利に活用できます。
住所 北海道沙流郡日高町字富岡
電話番号 01457-6-2922
開設期間 4月下旬~10月中旬
営業時間 チェックイン13:00~、チェックアウト~翌11:00
料金(1泊) 施設維持費:小学生以上100円+オートサイト1300~3000円
※ペット可(Cサイトのみ)、ゴミ処理可